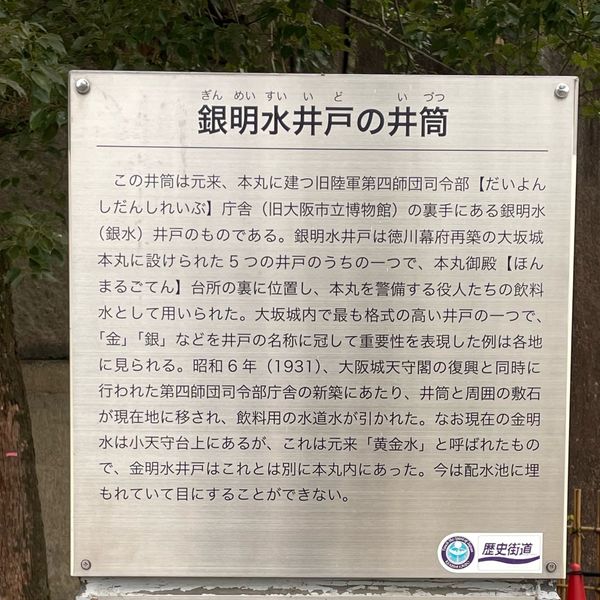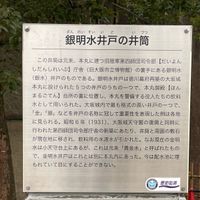ここがあの場所!身近な場所の歴史
実は、街なかには隠れた歴史的名所がたくさん!旅先だけでなく、近所の散歩でも意外な名所が見つかるかも?!歴史の勉強や小学生の自由研究にもおすすめです。紹介されていないスポットを見つけたら、みんなで登録して共有しよう!
関連するめっけブック
関連するめっけブック
紹介スポット
- 8106件
聖路加国際病院のすぐ近くにある古代ギリシアの神殿風の建物が,東京最古のカトリック教会といわれるカトリック築地教会です。 ここに初めて教会が建てられたのは,1878(明治11)年のこと。フランスのパリ外国宣教会に所属する宣教師マラン神父とミドン神父によって,外国人居留地内だった現在地に赤レンガ,ゴシック様式の「築地司教座聖堂」が建てられました。当時の聖堂は,長崎の大浦天主堂に匹敵する建物だったと伝えられています。 以後,築地教会は東京以北の宣教の中心となっていましたが,1923(大正12)年の関東大震災で聖堂が倒壊してしまいます。現在の聖堂は1926(大正15)年に再建されたもので,一見すると石造りに見えますが実は木造モルタル造,震災後の厳しい状況の下で苦心して建てられたことが窺われます。 太平洋戦争では,聖路加国際病院の近くにあったため空襲の被害を免れたといわれます。旧聖堂の時代から使われてきた銅製の洋鐘は,1876(明治9)年にフランスでつくられたもので,現在も教会の敷地内に保存されています。

聖路加国際病院のすぐ近くにある古代ギリシアの神殿風の建物が,東京最古のカトリック教会といわれるカトリック築地教会です。 ここに初めて教会が建てられたのは,1878(明治11)年のこと。フランスのパリ外国宣教会に所属する宣教師マラン神父とミドン神父によって,外国人居留地内だった現在地に赤レンガ,ゴシック様式の「築地司教座聖堂」が建てられました。当時の聖堂は,長崎の大浦天主堂に匹敵する建物だったと伝えられています。 以後,築地教会は東京以北の宣教の中心となっていましたが,1923(大正12)年の関東大震災で聖堂が倒壊してしまいます。現在の聖堂は1926(大正15)年に再建されたもので,一見すると石造りに見えますが実は木造モルタル造,震災後の厳しい状況の下で苦心して建てられたことが窺われます。 太平洋戦争では,聖路加国際病院の近くにあったため空襲の被害を免れたといわれます。旧聖堂の時代から使われてきた銅製の洋鐘は,1876(明治9)年にフランスでつくられたもので,現在も教会の敷地内に保存されています。
かつての築地市場があった辺り,もと外国人居留地の南に接するところに軍艦操練所がありました。これは,洋式軍艦の操縦法を教授するため江戸幕府が設けた施設です。 その跡地に建てられたのが日本初の本格的な洋風ホテル,築地ホテル館。設計にあたったのはアメリカ人技師R.P.ブリジェンスと横浜で洋風建築の技術を学んだ清水組(現在の清水建設)二代目の清水喜助でした。 竣工したのは1868(慶応4)年,幕府はすでに崩壊していました。ホテル館は,中央に塔屋がそびえる擬洋風の木造2階建て。瓦屋根で外側はなまこ壁,内壁には漆喰が塗られていました。客室は全102室で水洗トイレが付き,シャワー室やビリヤード室,バーも備えられていたといいます。 築地ホテル館は東京の新名所として評判となり,多くの人々が見物に訪れ,錦絵にも描かれました。しかし,築地での貿易が振わなかったため宿泊客は多くなく,1872(明治5)に起きた京橋一帯の大火によって焼失してしまいました。 タイムドーム明石(中央区明石町12-1 中央区保健所等複合施設6階)に築地ホテル館の立体模型が展示されています。

かつての築地市場があった辺り,もと外国人居留地の南に接するところに軍艦操練所がありました。これは,洋式軍艦の操縦法を教授するため江戸幕府が設けた施設です。 その跡地に建てられたのが日本初の本格的な洋風ホテル,築地ホテル館。設計にあたったのはアメリカ人技師R.P.ブリジェンスと横浜で洋風建築の技術を学んだ清水組(現在の清水建設)二代目の清水喜助でした。 竣工したのは1868(慶応4)年,幕府はすでに崩壊していました。ホテル館は,中央に塔屋がそびえる擬洋風の木造2階建て。瓦屋根で外側はなまこ壁,内壁には漆喰が塗られていました。客室は全102室で水洗トイレが付き,シャワー室やビリヤード室,バーも備えられていたといいます。 築地ホテル館は東京の新名所として評判となり,多くの人々が見物に訪れ,錦絵にも描かれました。しかし,築地での貿易が振わなかったため宿泊客は多くなく,1872(明治5)に起きた京橋一帯の大火によって焼失してしまいました。 タイムドーム明石(中央区明石町12-1 中央区保健所等複合施設6階)に築地ホテル館の立体模型が展示されています。
立教大学など立教学院のルーツは,アメリカ聖公会の宣教師チャニング・M・ウィリアムズが,1974(明治7)年に築地の外国人居留地に開いた「立教学校」という名の私塾にあります。立教学校は,その後の大火事による移転や閉鎖を経て,1883(明治16)年には,ハーバード大学で建築学を修めたガーディナー校長のもと,築地外国人居留地37番に尖塔や礼拝堂,寄宿舎などを備えた本格的なレンガ校舎が完成し「立教大学校」と称するようになります。しかしこの校舎は1894(明治27)年の大地震で倒壊し,記念碑のある場所に移転することになりました。なお築地居留地37番には,後に聖路加病院が開設されます。 記念碑は立教大学卒業の彫刻家が制作したもので,立教学院創立125周年を記念して2000(平成12)年に建てられました。碑の前面には「すべての人に仕える者になりなさい」との聖マルコによる福音書の一説が刻まれています。なお,立教大学が現在の池袋に移ったのは1918(大正7)年のことです。

立教大学など立教学院のルーツは,アメリカ聖公会の宣教師チャニング・M・ウィリアムズが,1974(明治7)年に築地の外国人居留地に開いた「立教学校」という名の私塾にあります。立教学校は,その後の大火事による移転や閉鎖を経て,1883(明治16)年には,ハーバード大学で建築学を修めたガーディナー校長のもと,築地外国人居留地37番に尖塔や礼拝堂,寄宿舎などを備えた本格的なレンガ校舎が完成し「立教大学校」と称するようになります。しかしこの校舎は1894(明治27)年の大地震で倒壊し,記念碑のある場所に移転することになりました。なお築地居留地37番には,後に聖路加病院が開設されます。 記念碑は立教大学卒業の彫刻家が制作したもので,立教学院創立125周年を記念して2000(平成12)年に建てられました。碑の前面には「すべての人に仕える者になりなさい」との聖マルコによる福音書の一説が刻まれています。なお,立教大学が現在の池袋に移ったのは1918(大正7)年のことです。