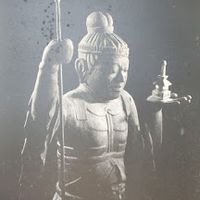大河ドラマでも注目!源頼朝の足跡を辿る
2022年度の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも注目度の高かった、源頼朝。 HP「yoritomo-japan.com」は源頼朝が創造した武家の都「鎌倉」とその関係地をめぐった記録。 今回、その「yoritomo-japan.com」にご協力いただき、紹介されているスポットをブックにしました! みなさまの歴史旅・歴史散歩のお供にぜひご覧ください。 ※営業状況等変更になっている可能性があります。お出かけの際は、事前にご確認ください。 yoritomo-japan.com
関連するめっけブック
関連するめっけブック
紹介スポット
- 404件芦の湯から精進池への国道1号線沿いに並ぶ三基の五輪塔は、曽我兄弟と虎御前のものと伝えられている(国重文)。 総高約2.5メートルの五輪塔で、左側2つが曽我兄弟のもので、右の少し低い塔が虎御前のもの。 虎御前の五輪塔には「永仁三年」(1295年)の銘が刻まれ、地蔵講によって建立されたことが判明している。 地蔵講の銘が刻まれているのは、この五輪塔が最古のものといわれている。 近くには地蔵信仰に基づく石仏群が存在する。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hakone-soga...

芦の湯から精進池への国道1号線沿いに並ぶ三基の五輪塔は、曽我兄弟と虎御前のものと伝えられている(国重文)。 総高約2.5メートルの五輪塔で、左側2つが曽我兄弟のもので、右の少し低い塔が虎御前のもの。 虎御前の五輪塔には「永仁三年」(1295年)の銘が刻まれ、地蔵講によって建立されたことが判明している。 地蔵講の銘が刻まれているのは、この五輪塔が最古のものといわれている。 近くには地蔵信仰に基づく石仏群が存在する。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hakone-soga...
謡曲「曽我物」の舞台となった箱根神社。 境内には曽我兄弟を祀った曽我神社がある。 1193年(建久4年)5月28日、曽我十郎祐成と五郎時致の兄弟は、父河津祐通(祐泰)の仇として工藤祐経を討ち果たした(曽我兄弟の仇討ち)。 「曽我物」では、五郎時致は、箱根権現(箱根神社)の稚児の頃、父の仇工藤祐経と会うが、討ち果たすことができず、祐経の人形を作って調伏したと描かれている。 また、兄祐成は、弟時致の元服を箱根権現の別当行実に願い出たと描かれている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hakone-soga...

謡曲「曽我物」の舞台となった箱根神社。 境内には曽我兄弟を祀った曽我神社がある。 1193年(建久4年)5月28日、曽我十郎祐成と五郎時致の兄弟は、父河津祐通(祐泰)の仇として工藤祐経を討ち果たした(曽我兄弟の仇討ち)。 「曽我物」では、五郎時致は、箱根権現(箱根神社)の稚児の頃、父の仇工藤祐経と会うが、討ち果たすことができず、祐経の人形を作って調伏したと描かれている。 また、兄祐成は、弟時致の元服を箱根権現の別当行実に願い出たと描かれている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hakone-soga...
1193年(建久4年)、源頼朝が催した富士の巻狩りで父の仇・工藤祐経を討とうと決心した曽我兄弟。 この滝の近くで討ち入りの密議をしていたが、滝の轟音で声がかき消されてしまうので、念じたところ滝の音が止んだのだと伝えられている。 そして、密議が済むと再び滝の音が轟いたのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/otodom...

1193年(建久4年)、源頼朝が催した富士の巻狩りで父の仇・工藤祐経を討とうと決心した曽我兄弟。 この滝の近くで討ち入りの密議をしていたが、滝の轟音で声がかき消されてしまうので、念じたところ滝の音が止んだのだと伝えられている。 そして、密議が済むと再び滝の音が轟いたのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/otodom...
曽我兄弟が討ち入りの密議を行った場所と伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/fuji-m...

曽我兄弟が討ち入りの密議を行った場所と伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/fuji-m...
1193年(建久4年)5月、源頼朝が催した富士裾野の巻狩りに同行していた工藤祐経は、5月28日夜半、雷雨の中、曽我兄弟に討ち入られ最期を遂げた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/fuji-m...

1193年(建久4年)5月、源頼朝が催した富士裾野の巻狩りに同行していた工藤祐経は、5月28日夜半、雷雨の中、曽我兄弟に討ち入られ最期を遂げた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/fuji-m...
1193年(建久4年)、源頼朝が催した富士裾野の巻狩り。 この時に起こったのが曽我兄弟の仇討ち。 見事に親の仇を討った曽我兄弟だったが、兄の十郎祐成は仁田忠常に討たれ、弟の五郎時致は捕えられて処刑された。 曽我兄弟の墓の辺りには仁田忠常の陣所が置かれていたといわれ、兄の十郎祐成が討たれた場所といわれる。 「露とのみ消えにしあとを来てみれば尾花が末に秋風ぞ吹く」 十郎祐成の愛人だった虎御前は、兄弟の終焉の地を訪れてこう詠んだのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/fuji-m...

1193年(建久4年)、源頼朝が催した富士裾野の巻狩り。 この時に起こったのが曽我兄弟の仇討ち。 見事に親の仇を討った曽我兄弟だったが、兄の十郎祐成は仁田忠常に討たれ、弟の五郎時致は捕えられて処刑された。 曽我兄弟の墓の辺りには仁田忠常の陣所が置かれていたといわれ、兄の十郎祐成が討たれた場所といわれる。 「露とのみ消えにしあとを来てみれば尾花が末に秋風ぞ吹く」 十郎祐成の愛人だった虎御前は、兄弟の終焉の地を訪れてこう詠んだのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/fuji-m...
1197年(建久8年)、曽我兄弟の孝心に感心した源頼朝が、畠山重忠を遣わして、この地の住人・渡辺主水が創建したという社。 祭神は応神天皇。 曽我十郎祐成・曽我五郎時致・虎御前が相殿として祀られている。 主神の応神天皇の尊像は、伊豆国の蛭ヶ小島に流されていた頼朝に文覚が贈ったものと伝えられる騎馬像。 曽我兄弟と虎御前の像は、畠山重忠が丹波法源に刻ませたものと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/fuji-m...

1197年(建久8年)、曽我兄弟の孝心に感心した源頼朝が、畠山重忠を遣わして、この地の住人・渡辺主水が創建したという社。 祭神は応神天皇。 曽我十郎祐成・曽我五郎時致・虎御前が相殿として祀られている。 主神の応神天皇の尊像は、伊豆国の蛭ヶ小島に流されていた頼朝に文覚が贈ったものと伝えられる騎馬像。 曽我兄弟と虎御前の像は、畠山重忠が丹波法源に刻ませたものと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/fuji-m...
1190年(建久元年)、上洛を果たした源頼朝は、鞍馬寺を訪れた際に、行基作と伝わる毘沙門天像二体のうちの一体を賜った。 翌年、その毘沙門天像を安置するために建立された毘沙門堂が白山神社の始まりだと伝えられている。 鞍馬寺が平安京の北東の鎮護であることから、鎌倉の北東に当たる今泉の地に安置されたのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/page140haku...

1190年(建久元年)、上洛を果たした源頼朝は、鞍馬寺を訪れた際に、行基作と伝わる毘沙門天像二体のうちの一体を賜った。 翌年、その毘沙門天像を安置するために建立された毘沙門堂が白山神社の始まりだと伝えられている。 鞍馬寺が平安京の北東の鎮護であることから、鎌倉の北東に当たる今泉の地に安置されたのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/page140haku...
後白河天皇は、第77代天皇。 1155年(久寿2年)、29歳で即位。 1158年(保元3年)、二条天皇に譲位して院政を開始。 1169年(仁安3年)、法住寺殿で出家して法皇になる。 1192年(建久3年)3月13日、六条殿で崩御(66歳)。 法住寺殿の一画に建立された法華堂に葬られた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

後白河天皇は、第77代天皇。 1155年(久寿2年)、29歳で即位。 1158年(保元3年)、二条天皇に譲位して院政を開始。 1169年(仁安3年)、法住寺殿で出家して法皇になる。 1192年(建久3年)3月13日、六条殿で崩御(66歳)。 法住寺殿の一画に建立された法華堂に葬られた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...
忍野八海に鎮座する忍草(しぼくさ)浅間神社は807年(大同2年)の創建。 一般には「忍野八海の浅間神社」と呼ばれている。 1193年(建久4年)、富士裾野の巻狩りを催した源頼朝は、鳥居崎鬼坂までを社領と定めたと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/osinoh...

忍野八海に鎮座する忍草(しぼくさ)浅間神社は807年(大同2年)の創建。 一般には「忍野八海の浅間神社」と呼ばれている。 1193年(建久4年)、富士裾野の巻狩りを催した源頼朝は、鳥居崎鬼坂までを社領と定めたと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fuji/osinoh...